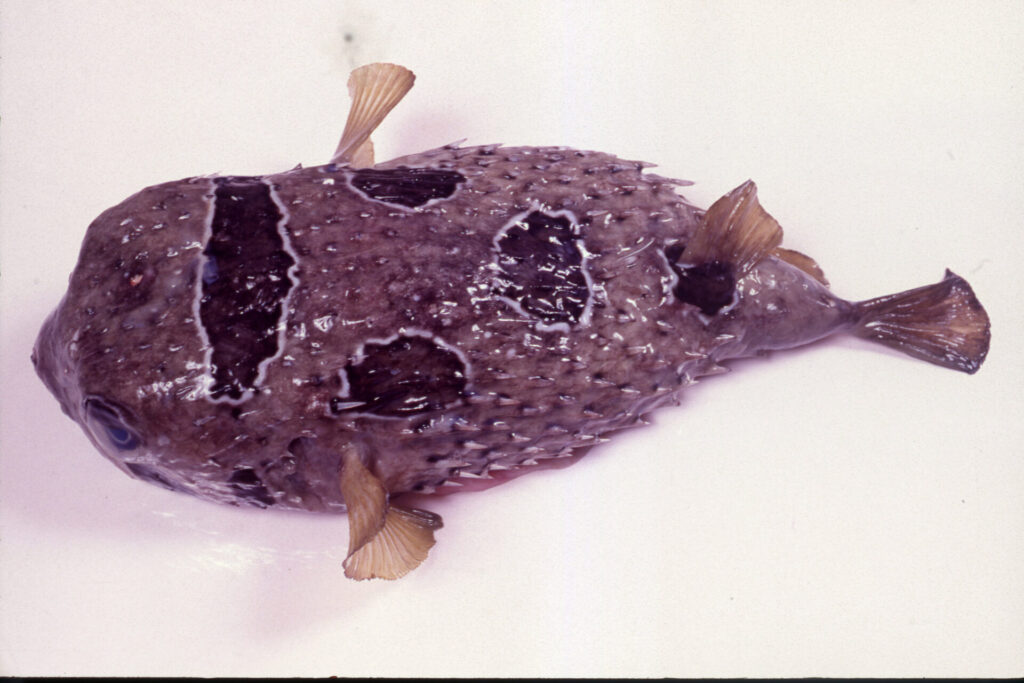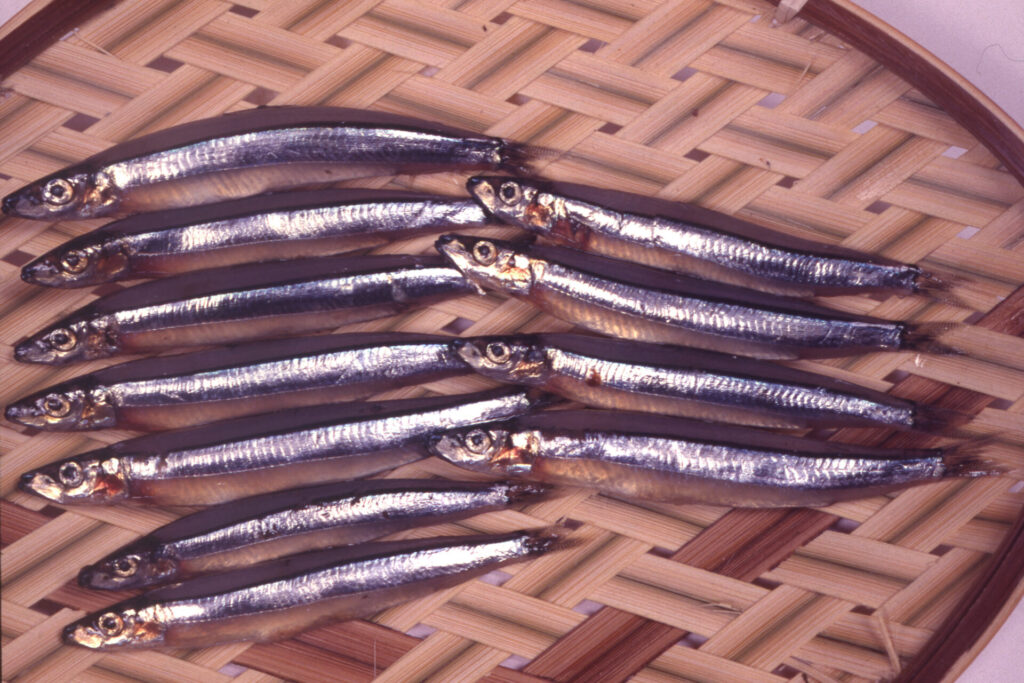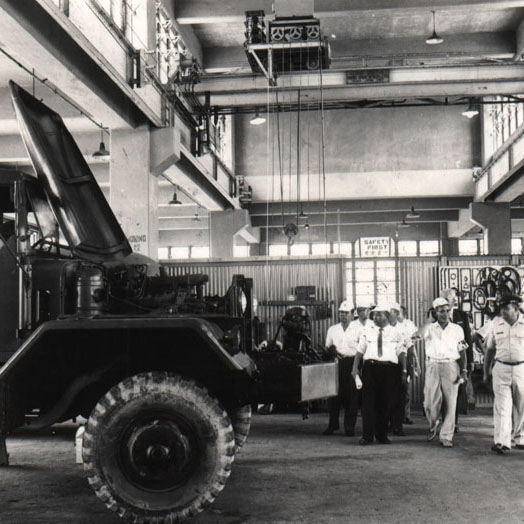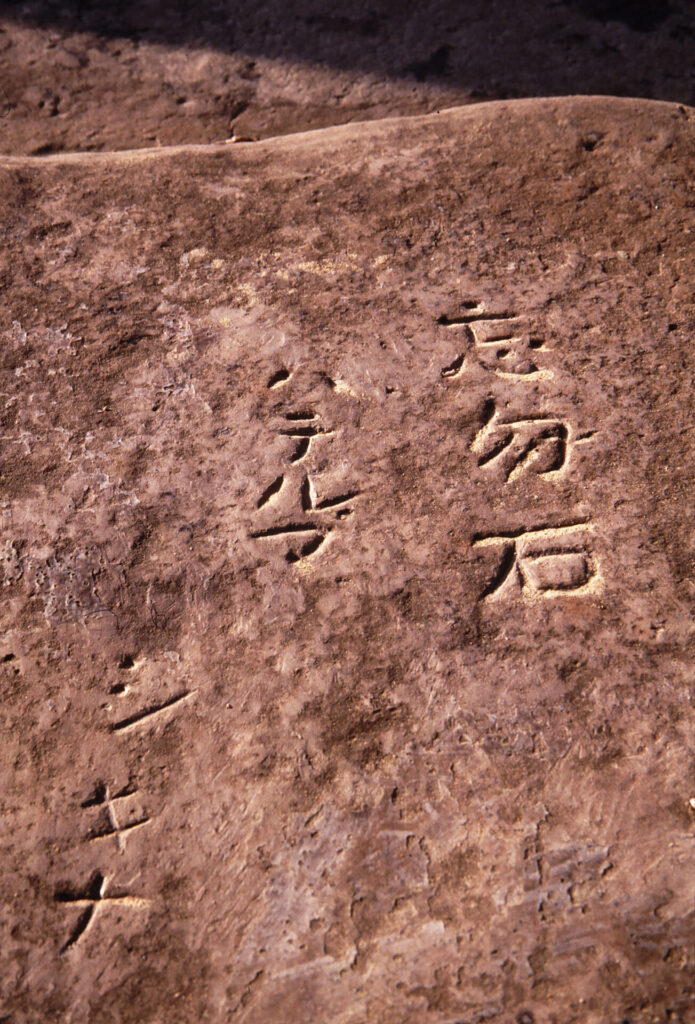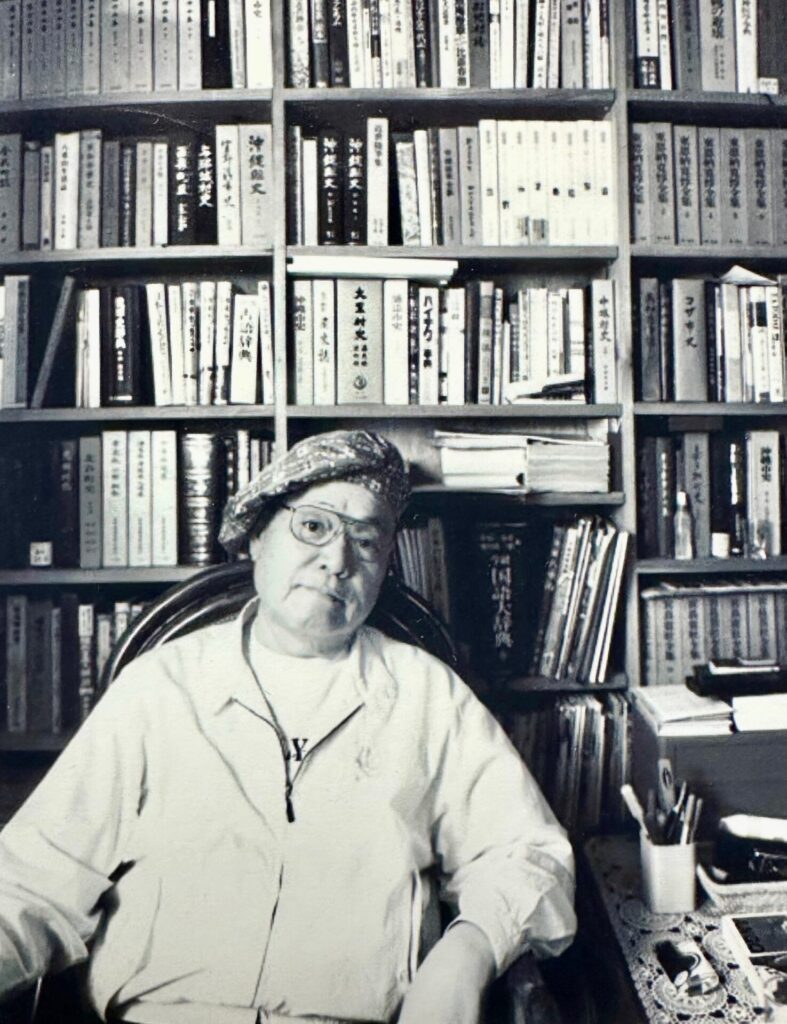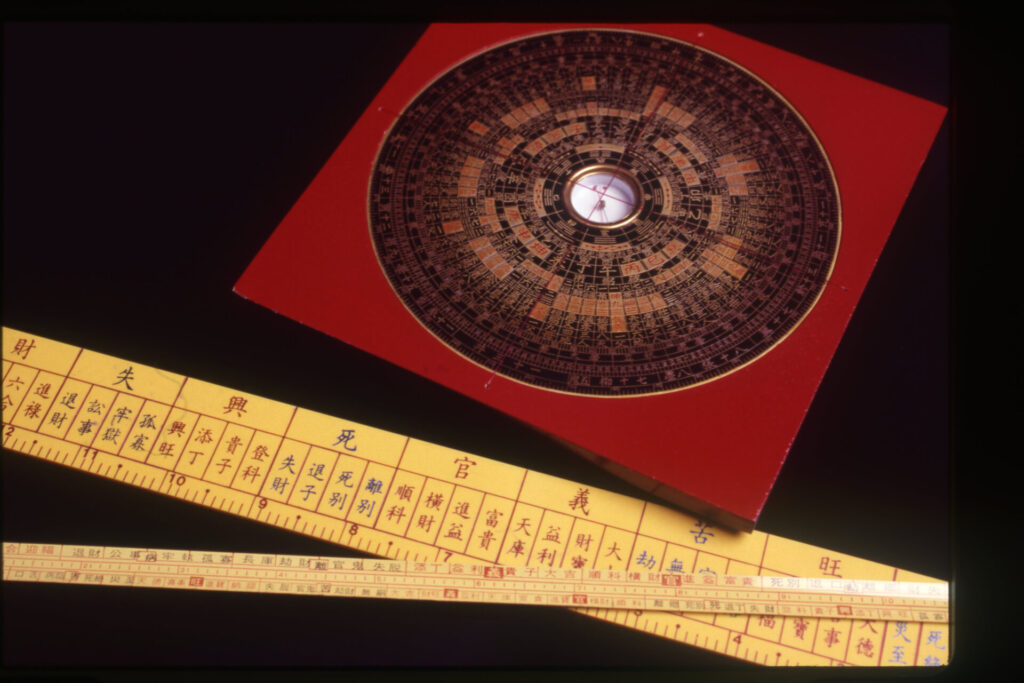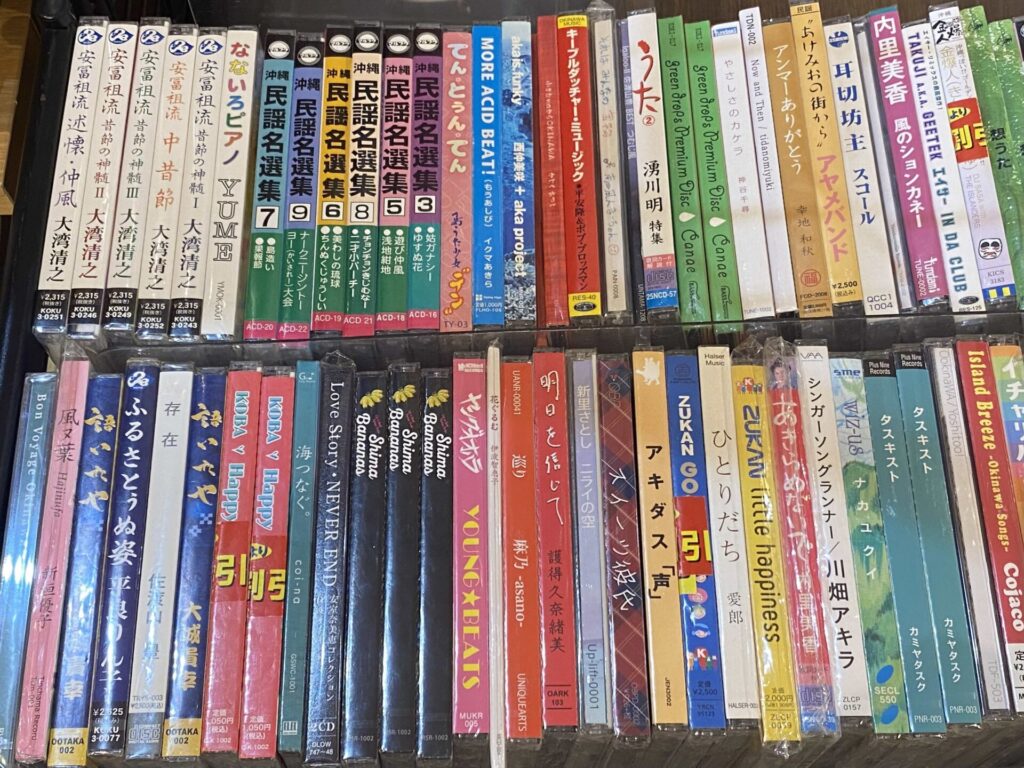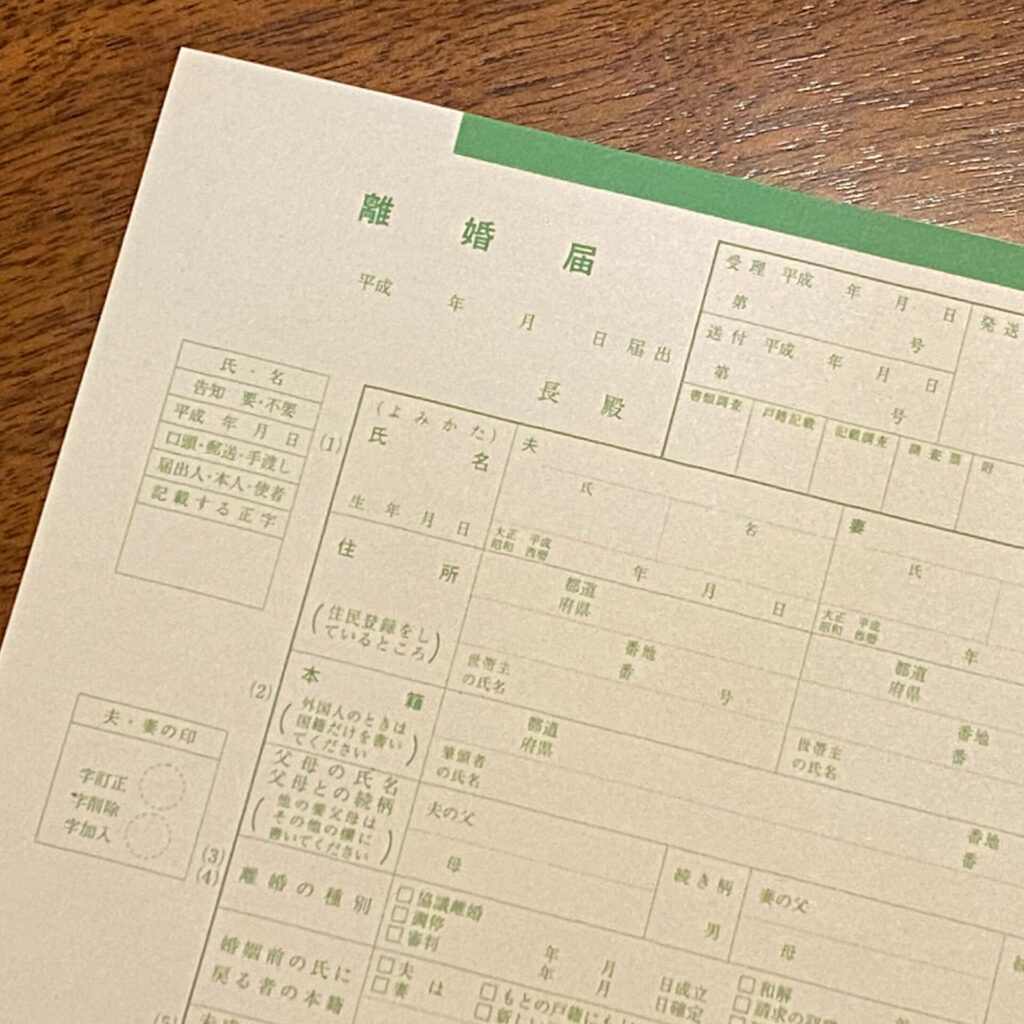沖縄映画
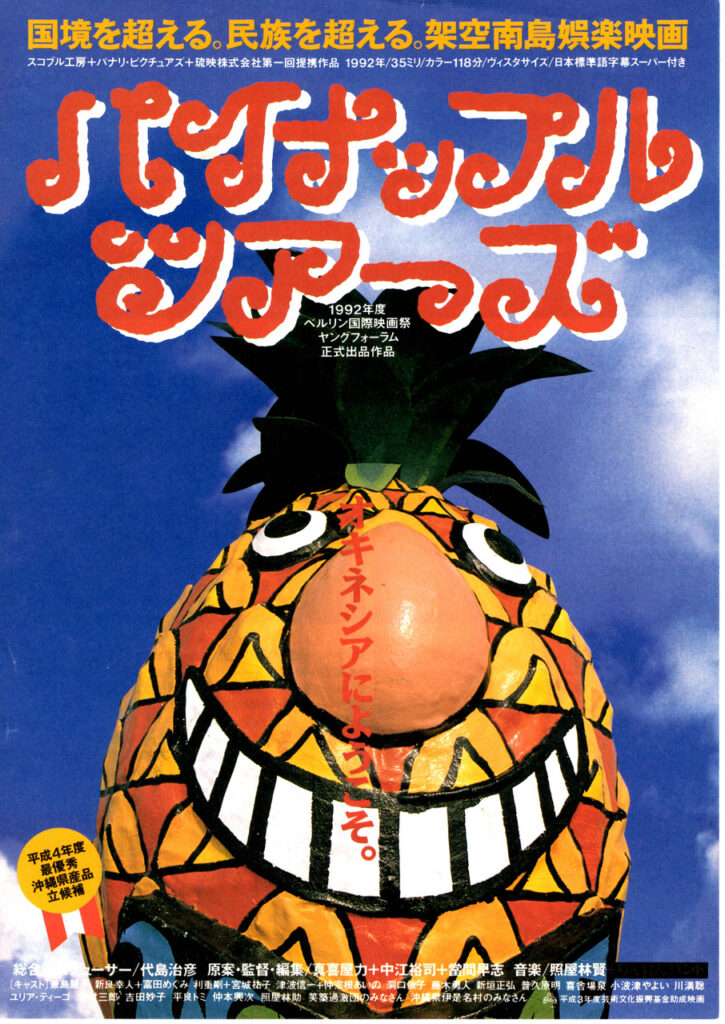
http://pineapple-tours.com
沖縄で撮られた映画、沖縄を舞台にした映画、沖縄が題材に使われている映画。面倒くさいから、それらをまとめて「オキネシマ」と名付けよう(造語だよ)。さて、このオキネシマ、いろいろ調べてみると、1931年に撮られた『執念の毒蛇』が、現存する最古の作品らしい。ハワイ帰りのウチナーンチュ・渡口政善氏が製作と脚本を手掛けた怪談モノのサイレントで、88年に新報ホールにて再映されたときに見た。沖縄芝居の役者・北村三郎さんによる弁士付きだ。当時の沖縄の風景を楽しもうと思っていたのに、全体的に室内シーンが多く、内容もあまり沖縄と関係なかったような気がする。稚拙な演出で、映画のデキとしては今イチだけど、北村さんの弁士ぶりが面白かったから、OK。監督は、早撮りの得意な吉野二郎という人で、41年にも『白い壁画』(月形龍之介出演)という八重山を舞台にしたオキネシマを、沖縄本島で撮っている。
戦後から60年ごろまでは、沖縄芝居の人たちが劇団単位でいくつか撮っていたようだ。舞台芝居に映画を導入する連鎖劇も多かったらしい。是非、今の沖縄芝居にも、当時のような連鎖劇を復活させてほしいものだ。
ウルトラマンを生んだ金城哲夫も、沖縄芝居の人たちとともに『吉屋チルー物語』(61年)を撮っている。彼が円谷プロに入社する前の弱冠24歳のときの作品だ。処女作のわりには、映画としての形がしっかりとしていて、金城哲夫の創作に対する情熱と才能には、ホント、脱帽するよ。
そうそう、沖縄で連鎖劇が盛んだったころの56年に撮られた珍作オキネシマを忘れていた。マーロン・ブランドがウチナーンチュとして登場する『八月十五夜の茶屋』というハリウッドの喜劇だ。終戦直後の沖縄が舞台だけど、撮影は本土とハリウッド。あの淀川長治も一シーンだけ出演している(しかも台詞有り)。ウチナーンチュの芸者(?)を演じた京マチ子は、登場シーンが少ないにもかかわらず、美しく存在感があって、さすが大女優って感じ。日本と沖縄を混同した世界観の中に、「ピィージャー(山羊)」という台詞や、ウチナーンチュはノンビリしてるから日本に占領されたというような会話があったりして、「沖縄」という視点から見ても好感のもてる作品だ。
ハリウッドが描いた近年のオキネシマには、『ベストキッド2』(86年)があるけど、ロケハンで来沖したスタッフが「オキナワのイメージと違う!」ということで、ハワイで撮影。でんでん太鼓が出てきたり、中国人のような衣装をまとったりと、『八月~』以上に東洋のイメージがゴッチャまぜになっていて、そこには、僕らも見たことのない「OKINAWA」がある。そのメチャクチャな沖縄のいじり方はくだらなくて面白いけど、それを抜きにするとひどい作品だ。
沖縄をリアルに描いていないオキネシマを見て、「こんなの沖縄じゃない!」と一蹴するウチナーンチュって多いと思う(僕も一時期そうだった)。それって、強い地元意識のマイナス面かもしれない。作品にとって不幸だ。オキネシマは、必ず「沖縄」をキチンと描いてなきゃいけないってワケじゃない。沖縄の人・自然・芸能なんかを利用して、面白くすりゃイイのだ。…んだけど、大かたのオキネシマが、映画としての面白さを忘れて、「無理やり琉球民謡のBGM」とか、「強引なカチャーシー」とか、沖縄に頼った描き方をしているんだから、客からそういう基準で見られるのも仕方ないか。
その点、北野武監督が撮った2本のオキネシマ、『3‐4×10月』(90年)と『ソナチネ』(93年)はイイぞ。沖縄を描こうとする気負いがないから違和感がなく、武の目を通してみた沖縄に、新鮮さすら感じる。僕もその姿勢を見習いたいな。